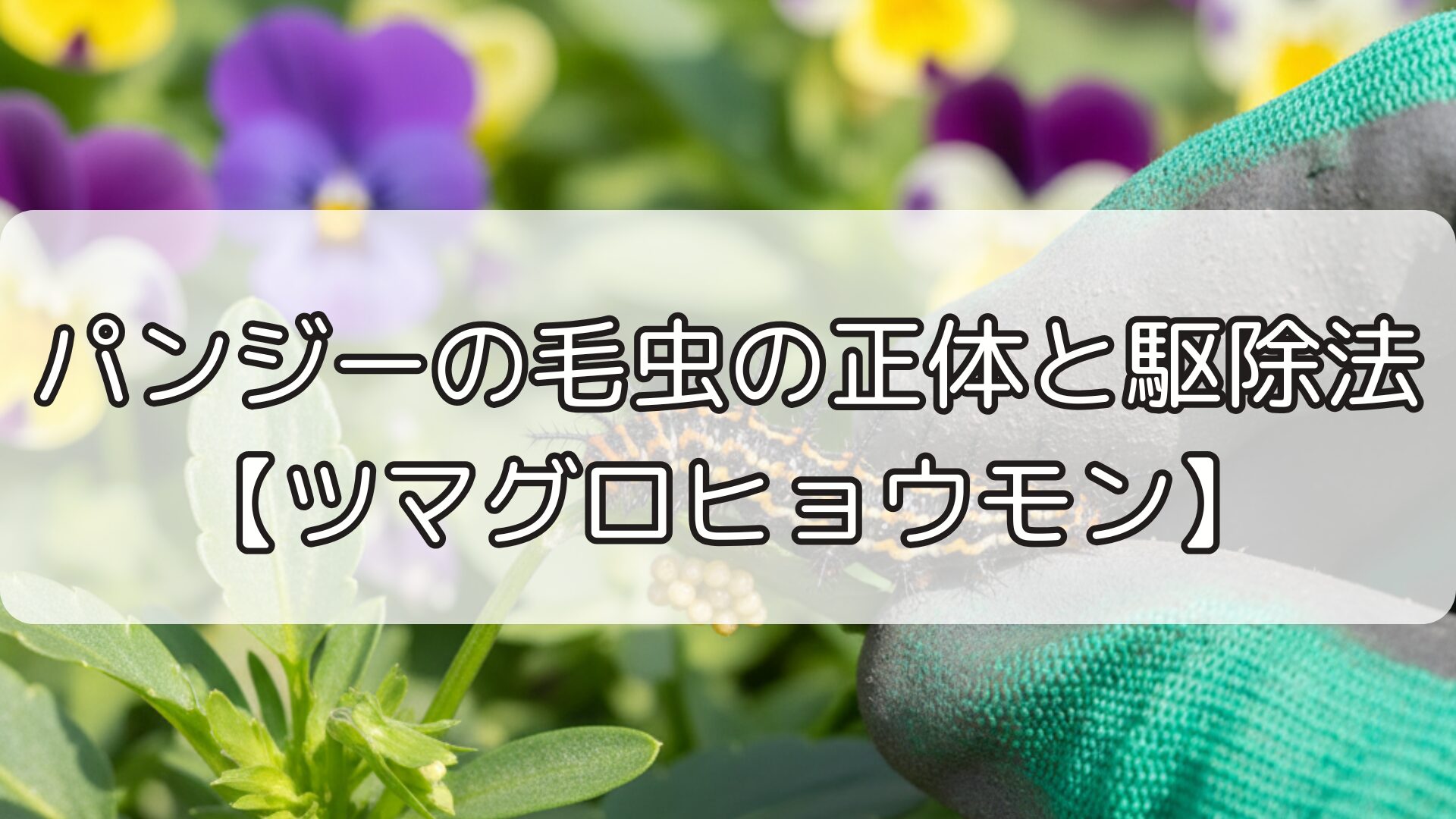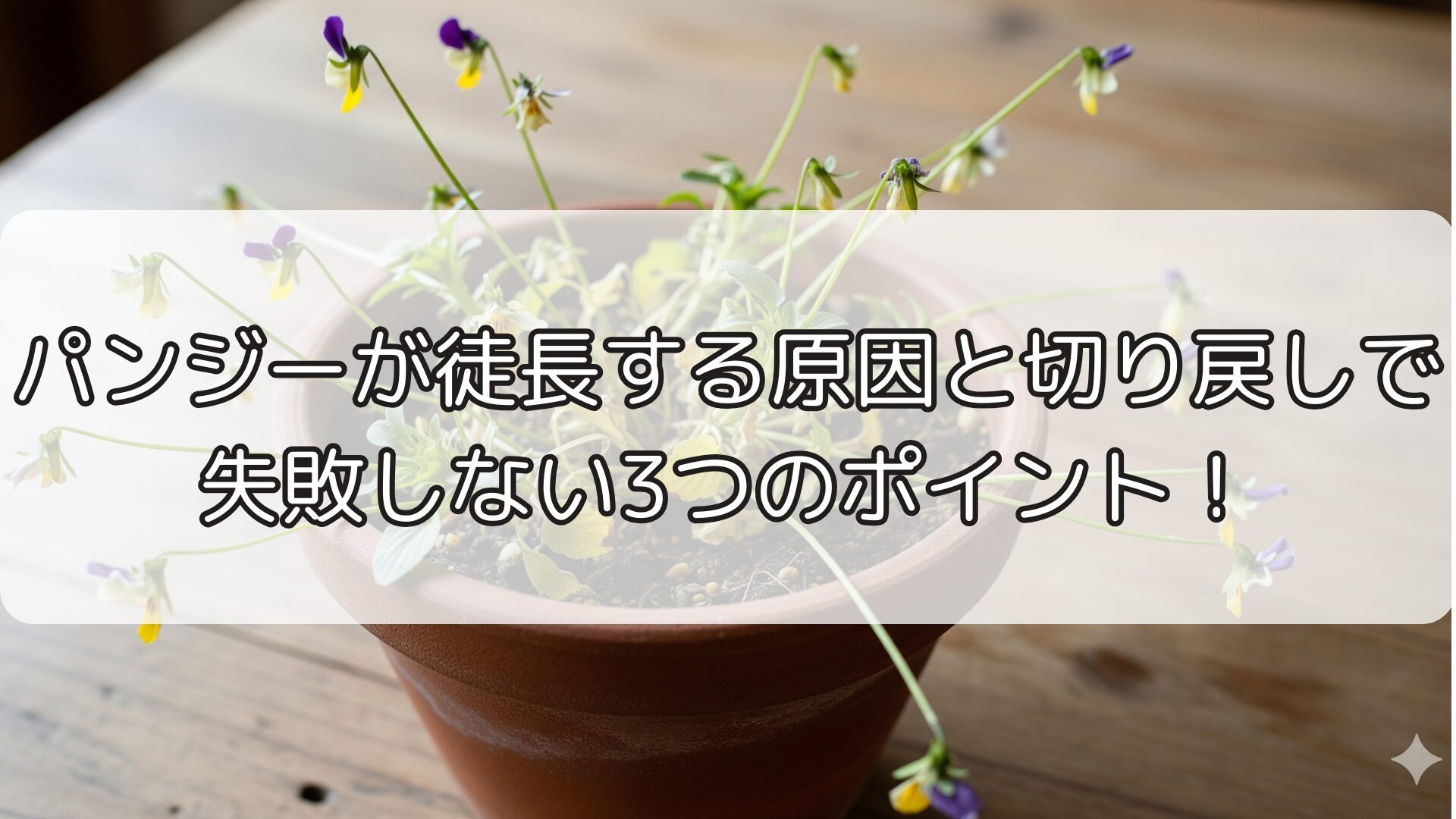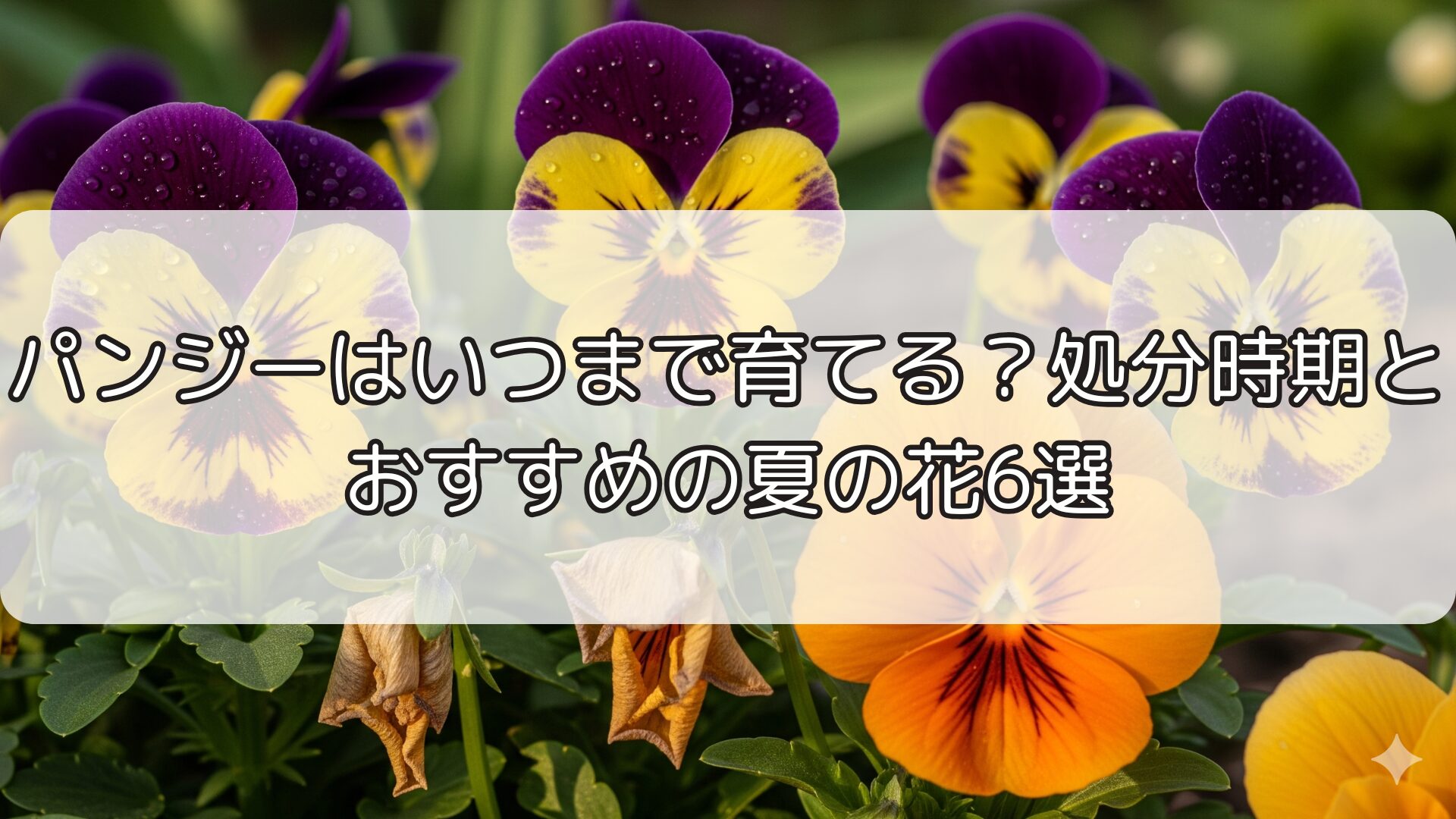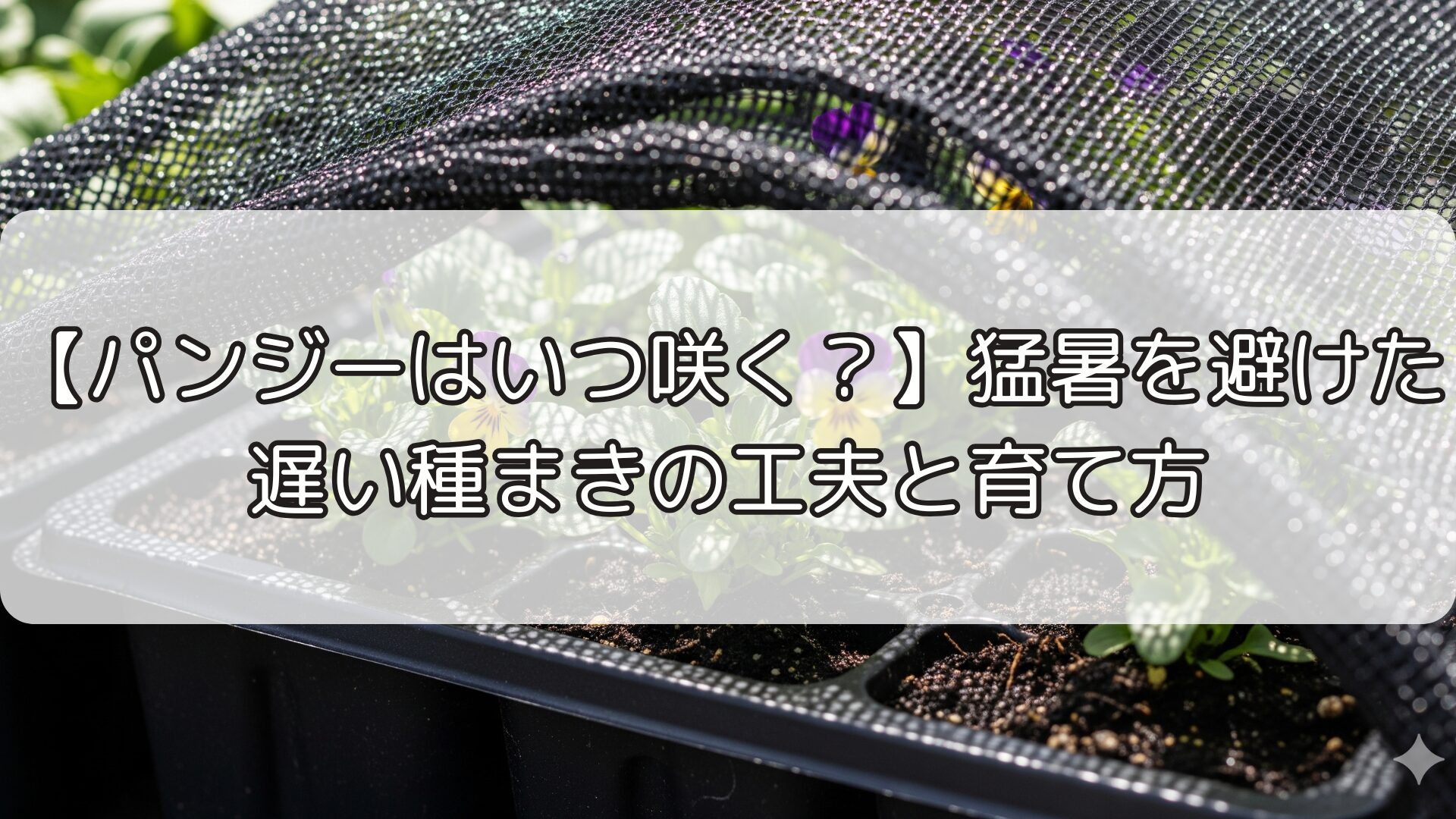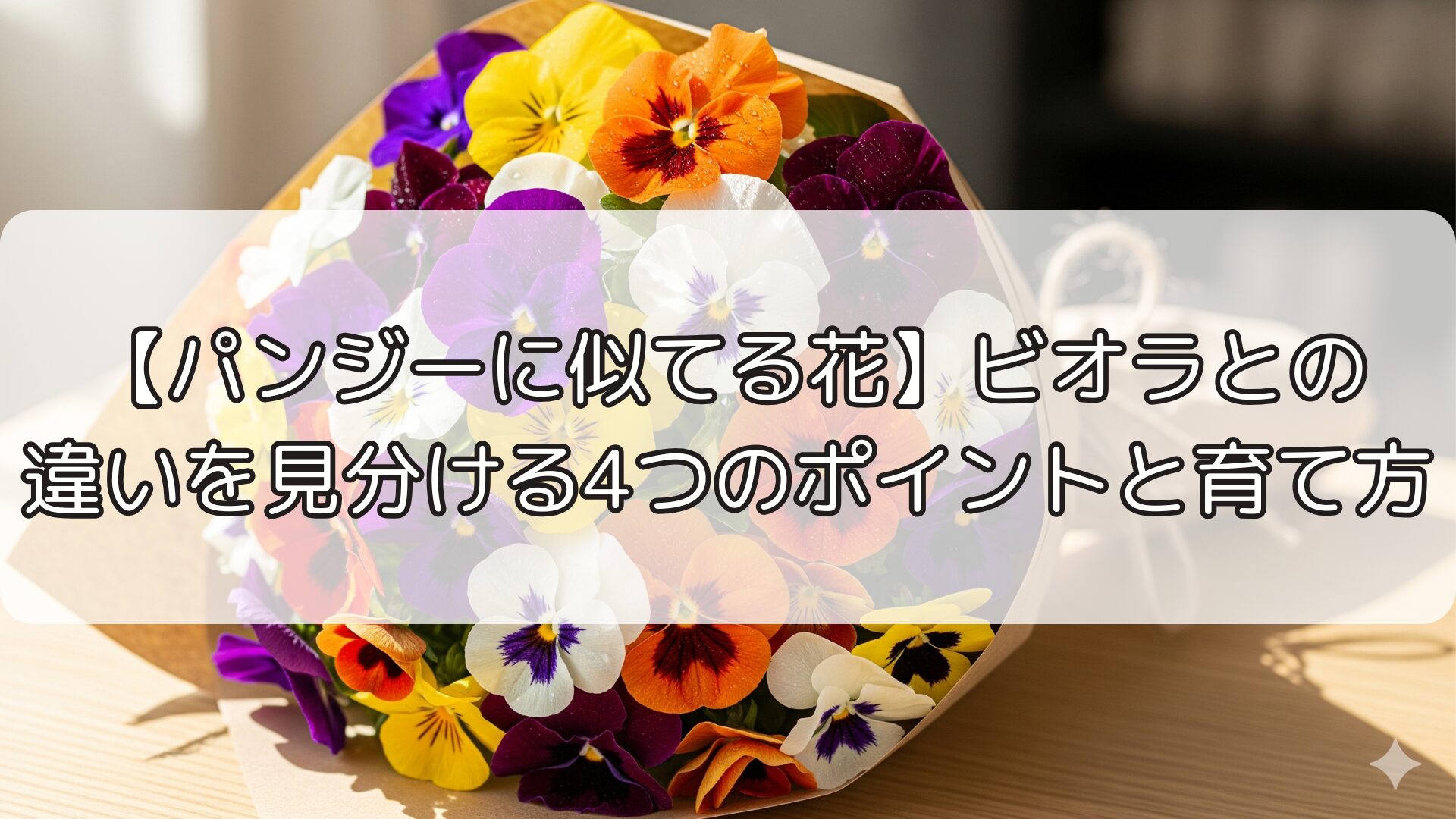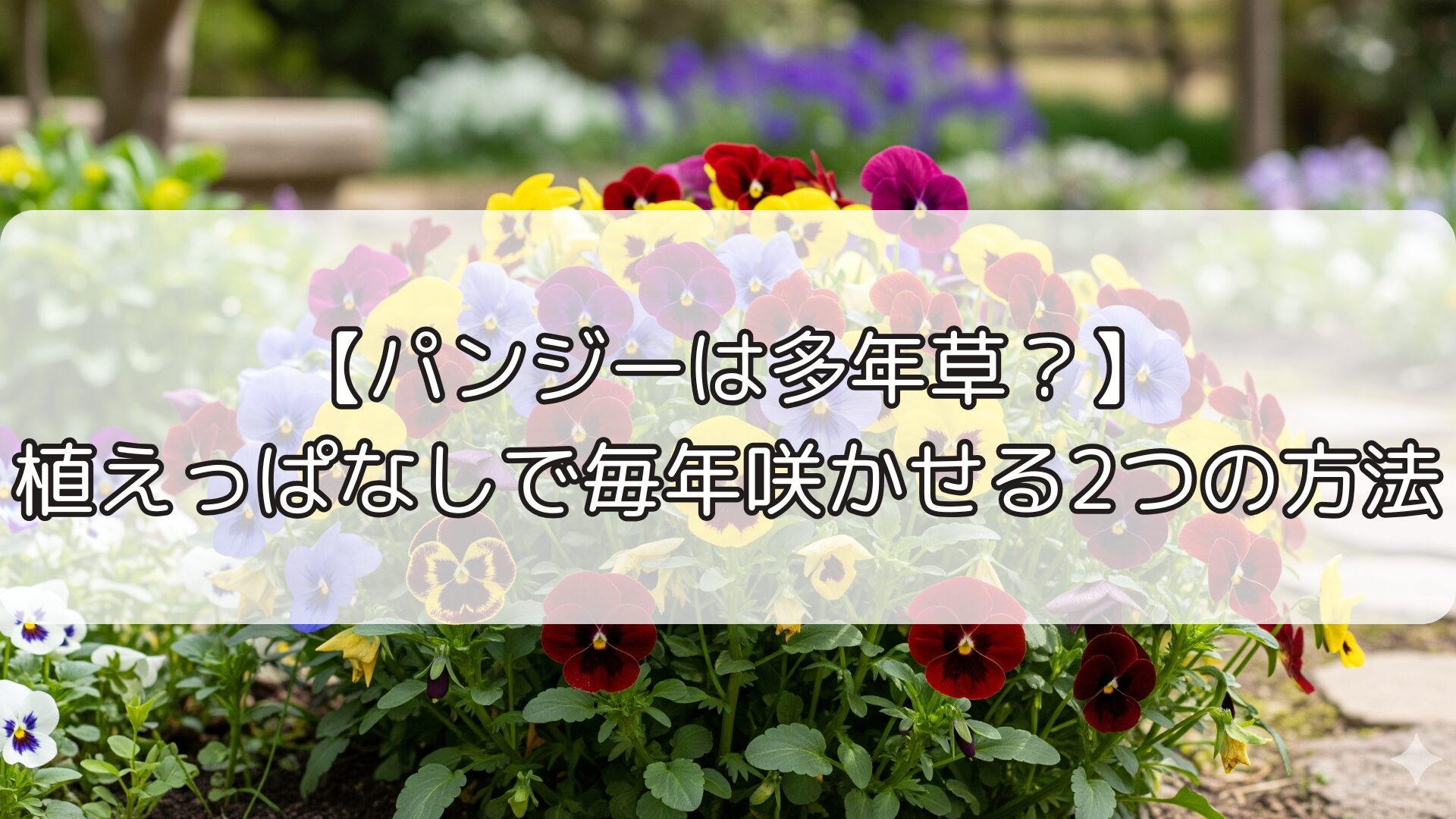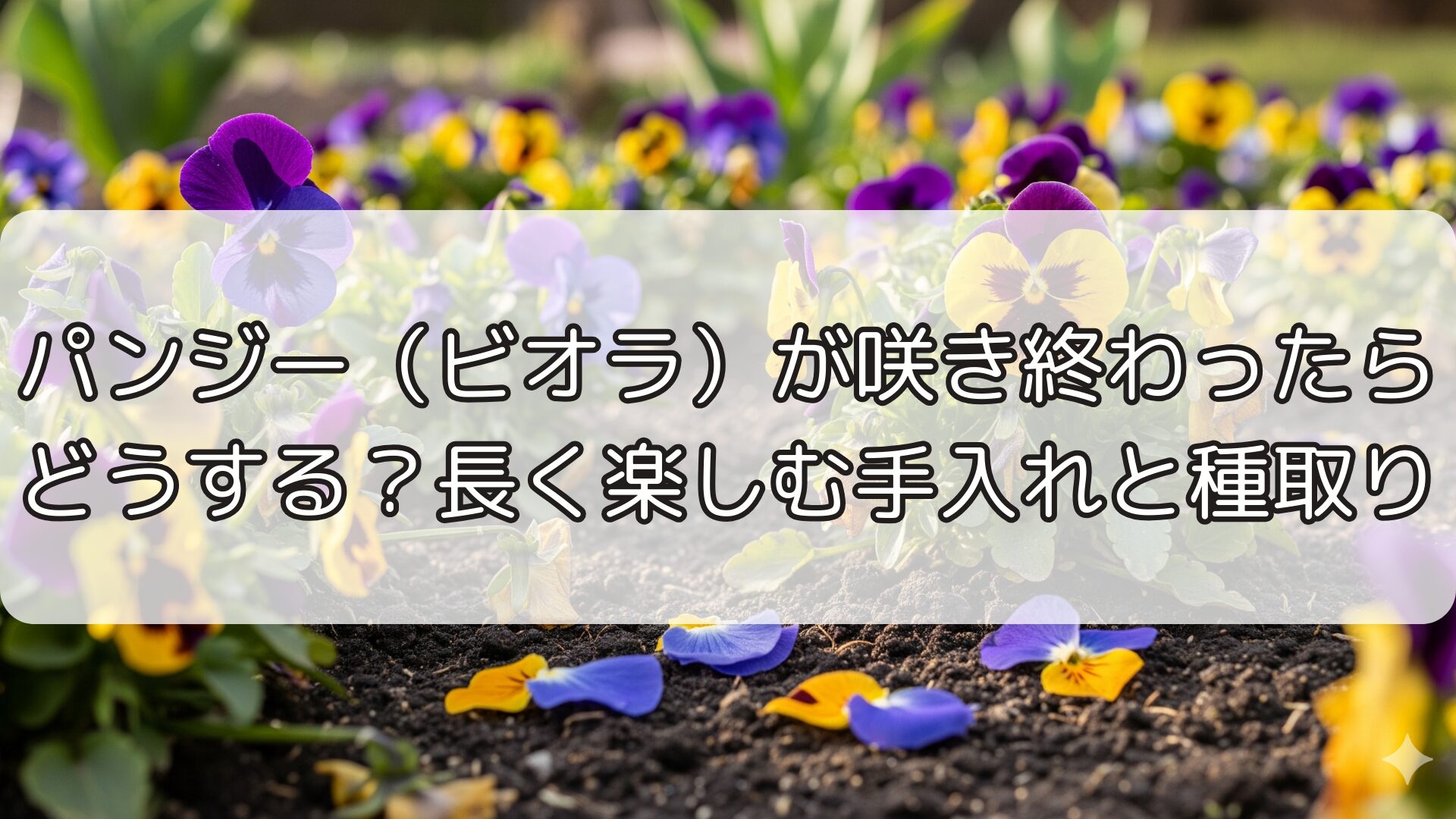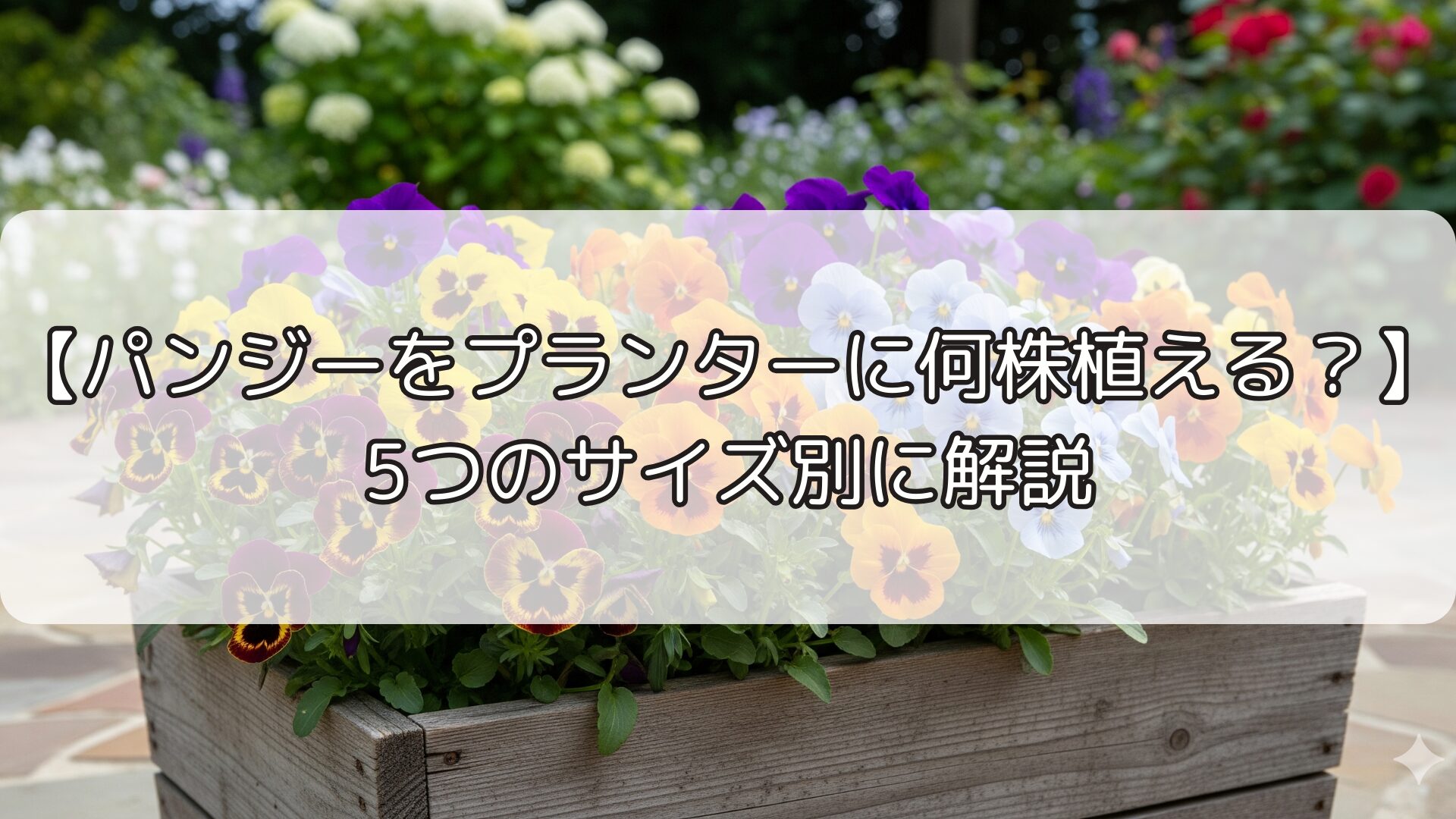パンジーの毛虫の正体と駆除法【ツマグロヒョウモン】
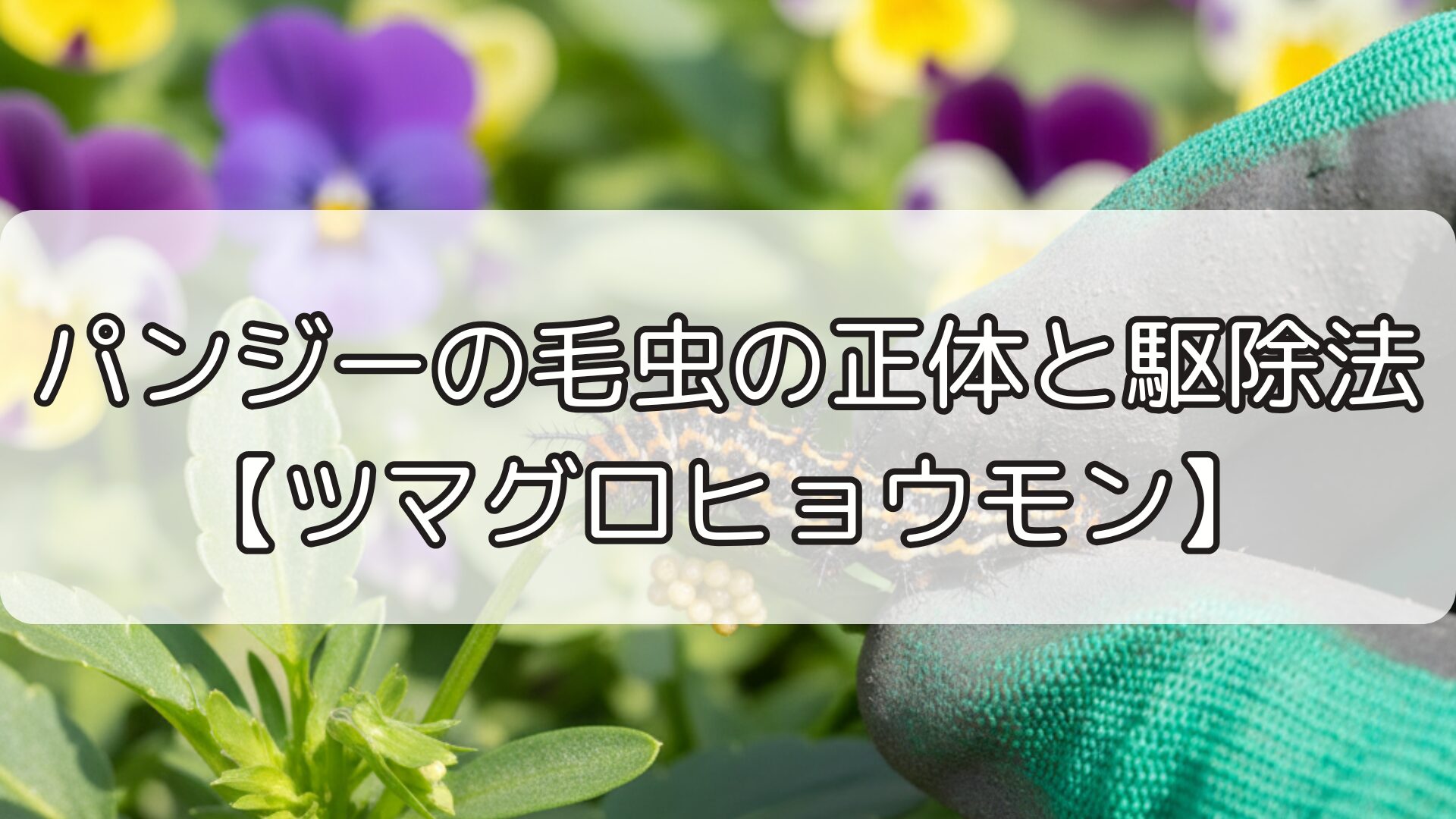
大切に育てているパンジーに、いつの間にか毛虫がついていて困っていませんか?パンジーで見かける黒とオレンジの毛虫は何になるのか、その正体はツマグロヒョウモンの幼虫かもしれません。
ツマグロヒョウモンの幼虫に毒はあるのか、どこから来るのか、また天敵はいるのか気になりますよね。特にツマグロヒョウモンの幼虫が大量発生した場合の駆除方法も知りたいところです。
一方で、毛がフサフサした黒とオレンジの毛虫には毒を持つ危険な種類もいるため、正しい知識で見分けることが重要になります。
- パンジーにつく毛虫の正体
- ツマグロヒョウモン幼虫の安全な駆除方法
- 注意すべき毒毛虫の種類と対策
- 薬剤を使用する際のポイント
パンジーの毛虫の正体はツマグロヒョウモンかも

- ツマグロヒョウモンの生態とは?
- 黒とオレンジの毛虫は何になる?
- ツマグロヒョウモンの幼虫に毒はあるのか
- ツマグロヒョウモンの幼虫はどこから来る?
- ツマグロヒョウモン幼虫の大量発生の原因
- ツマグロヒョウモンの幼虫の天敵はいる?
ツマグロヒョウモンの生態とは?

パンジーやビオラでよく見かけるトゲトゲした毛虫の正体は、多くの場合「ツマグロヒョウモン」という蝶の幼虫です。この蝶はタテハチョウ科に属し、鮮やかなヒョウ柄模様の翅(はね)を持つのが特徴です。
もともとは西日本を中心に生息していましたが、近年の温暖化の影響で生息域を北へ広げ、今では関東地方でも頻繁に見かけるようになりました。
ツマグロヒョウモンの幼虫が好んで食べるのは、パンジーやビオラなどのスミレ科の植物です。そのため、ガーデニングでこれらの花を育てていると、成虫が卵を産み付けに来ることがあります。活動時期は長く、春先の4月頃から晩秋の11月頃まで、年に4~5回発生を繰り返します。
食欲旺盛な幼虫は、あっという間に葉や花を食べ尽くしてしまうため、ガーデニングを楽しむ人にとっては悩みの種になることも少なくありません。
黒とオレンジの毛虫は何になる?
黒い体にオレンジ色の筋が入り、トゲだらけの少し不気味な見た目をしている幼虫ですが、成長すると美しいオレンジ色の蝶に変身します。この劇的な変化は、まさに「みにくいアヒルの子」の物語を彷彿とさせます。
幼虫の期間を終えると、金色に輝くメダルのような突起がついた、とても特徴的でおしゃれな蛹(さなぎ)になります。そして、その蛹からヒョウ柄模様の美しい成虫が羽化するのです。
成虫のオスとメスの見分け方
ツマグロヒョウモンの成虫は、オスとメスで翅の模様が異なります。メスは前翅の先端が黒くなっており、その部分が光の当たり方によって青紫色に輝いて見えます。
一方、オスは全体的にオレンジ色のヒョウ柄模様で、メスのような黒い部分はありません。庭を飛んでいる蝶を観察して、オスかメスか見分けてみるのも面白いでしょう。
このように、見た目は害虫のようでも、美しい蝶になる益虫としての一面も持っています。そのため、すぐに駆除するのではなく、羽化まで見守るという選択をする人もいます。
ツマグロヒョウモンの幼虫に毒はあるのか

結論から言うと、ツマグロヒョウモンの幼虫に毒はありません。あのトゲトゲした威圧的な見た目は、鳥などの天敵から身を守るための「擬態(ぎたい)」であり、見かけ倒しなのです。そのため、素手で触っても毒による皮膚炎などを起こす心配はありません。
直接触れる際の注意点
毒はありませんが、幼虫の持つトゲは意外と硬いため、皮膚に刺さるとチクッと痛みを感じることがあります。肌が弱い方やお子様が触れる際には、念のため園芸用の手袋を着用するか、割り箸やトングなどを使って捕まえることをおすすめします。
このように、毒の心配はないため、過度に恐れる必要はありません。しかし、見た目がよく似た毛虫の中には毒を持つ種類もいるため、安易に「大丈夫だろう」と判断して素手で触るのは避けた方が賢明です。後述する毒毛虫との見分け方も参考にしてください。
ツマグロヒョウモンの幼虫はどこから来る?

ツマグロヒョウモンの幼虫は、成虫である蝶がパンジーやビオラの葉や茎に卵を産み付けることで発生します。彼らにとってスミレ科の植物は、幼虫が成長するために必要不可欠な唯一の食草なのです。成虫のメスは、幼虫の食草となる植物を正確に見つけ出し、そこに卵を産み付けます。
卵は直径1mmにも満たない非常に小さな黄色い粒で、葉の裏や茎などに一つずつ産み付けられるため、見つけるのは非常に困難です。そして、卵から孵化した幼虫は、すぐにその植物を食べ始め、脱皮を繰り返しながら大きくなっていきます。
もし庭にスミレ科の雑草が生えている場合、そこが発生源となっている可能性もあるでしょう。
ツマグロヒョウモン幼虫の大量発生の原因

近年、都市部でツマグロヒョウモンの幼虫が大量発生する背景には、いくつかの理由が考えられます。
大量発生の主な3つの原因
- 地球温暖化による生息域の拡大:前述の通り、もともと暖かい地域を好む蝶でしたが、温暖化によって冬を越せる地域が北上し、関東などでも繁殖が可能になりました。
- 都市環境への適応:幼虫の食草であるパンジーやビオラは、多くの家庭や公園の花壇で栽培されています。つまり、都市部はツマグロヒョウモンにとって「エサが豊富な楽園」となっているのです。
- 天敵の少なさ:都市部では、幼虫を捕食するアシナガバチやクモ、鳥などの天敵が少ない傾向にあります。これにより、幼虫の生存率が高まり、結果として個体数が増加しやすくなります。
これらの要因に加え、メス1匹あたりの産卵数が多いことや、年に複数回世代を繰り返す繁殖力の高さも、大量発生につながる一因と言えるでしょう。
ツマグロヒョウモンの幼虫の天敵はいる?

都市部では少ないとはいえ、自然界にはツマグロヒョウモンの幼虫を捕食する天敵が存在します。見た目の威嚇効果も万能ではなく、彼らにとって脅威となる生き物は少なくありません。
代表的な天敵としては、アシナガバチが挙げられます。アシナガバチは肉食で、蝶や蛾の幼虫を捕らえて巣に持ち帰り、自身の幼虫のエサにします。その他にも、カマキリやクモ、地上を徘徊するアリなども幼虫を襲うことがあります。
また、目には見えない天敵として、幼虫の体に卵を産み付けて内部から栄養を奪う「寄生バチ」の存在も知られています。
これらの天敵が周囲にいる環境では、ツマグロヒョウモンの数が自然と抑制されることもあります。しかし、確実に数を減らしたい場合は、天敵だけに頼るのではなく、人間が直接手を加える必要があります。
パンジーの毛虫の駆除と注意すべき危険な毛虫

- ツマグロヒョウモンの幼虫の駆除方法
- 駆除に使えるおすすめの薬剤
- 危険!毛虫で黒とオレンジでフサフサは要注意
ツマグロヒョウモンの幼虫の駆除方法

ツマグロヒョウモンの幼虫を駆除する方法は、主に「手作業での捕獲」と「薬剤の使用」の2つに分けられます。それぞれの状況に合わせて適切な方法を選びましょう。
手作業での物理的な駆除
数が少ない場合や、薬剤を使いたくない場合に最も確実な方法です。毒はないため比較的安全に行えますが、前述の通り、トゲが刺さる可能性を考慮して割り箸やピンセット、トングなどを使って一匹ずつ捕獲するのがおすすめです。捕獲した幼虫は、ビニール袋に入れて処分します。
発生を予防する方法
そもそも卵を産み付けさせないための予防策も効果的です。パンジーやビオラの苗を植え付けた後、目の細かい防虫ネットや、100円ショップなどで手に入る食卓カバーで覆っておくと、成虫の侵入を防ぐことができます。蝶が飛来し始める春先から対策しておくと良いでしょう。
駆除するのも一つの手ですが、せっかくなのでお子さんと一緒に観察してみてはいかがでしょうか?幼虫から美しい蝶へと変身する様子は、貴重な学びの機会になりますよ。食草のパンジーを少しおすそ分けする気持ちで見守るのも、ガーデニングの楽しみ方の一つかもしれません。
駆除に使えるおすすめの薬剤

大量に発生してしまい、手作業での駆除が追いつかない場合は、園芸用の殺虫剤を使用するのが効率的です。ツマグロヒョウモンのような蝶の幼虫には、「鱗翅目(りんしもく)の幼虫」に適用のある薬剤を選びましょう。
薬剤には大きく分けて2つのタイプがあります。
| タイプ | 特徴 | 代表的な薬剤例 |
|---|---|---|
| 粒剤(予防) | 土に撒くタイプ。成分が根から吸収され、植物全体に行き渡る。効果が長期間持続し、害虫の発生を予防するのに適している。 | オルトランDX粒剤 |
| スプレー剤(駆除) | 液体を直接散布するタイプ。即効性があり、既に発生している害虫を素早く駆除するのに適している。 | ベニカXファインスプレー、スミチオン乳剤 |
苗を植え付ける際に予防として粒剤を土に混ぜ込んでおき、それでも発生してしまった場合にスプレー剤で対処するのがおすすめです。
薬剤を使用する際の最重要注意点
園芸用殺虫剤は、人体や他の益虫に影響を与える可能性があります。使用する際は、必ず製品のラベルに記載されている使用方法、適用作物、希釈倍率などを厳守してください。また、散布時にはマスクや手袋、保護メガネを着用し、風のない日に行うなど、安全対策を徹底しましょう。
危険!毛虫で黒とオレンジでフサフサは要注意

パンジーで見かける黒とオレンジの毛虫が全てツマグロヒョウモンとは限りません。もし見つけた毛虫が、トゲトゲではなく長い毛で「フサフサ」している場合は、毒を持つ「ドクガ」の仲間の可能性があり、絶対に素手で触ってはいけません。
ドクガの仲間(チャドクガ、モンシロドクガなど)は、「毒針毛(どくしんもう)」という微細な毒の毛を持っており、これに触れると激しいかゆみや発疹を引き起こします。この毒針毛は非常に抜けやすく、風に乗って飛散することもあるため、直接触れなくても被害に遭うことがあります。
ツマグロヒョウモンとドクガの見分け方
- ツマグロヒョウモン:体は黒地にオレンジの筋。トゲ状の突起が規則正しく並んでいるが、毛は「フサフサ」していない。
- ドクガの仲間:体はオレンジと黒のまだら模様。長い毛が密集しており、全体的に「フサフサ」「もふもふ」した印象を受ける。
もしドクガと思われる毛虫を見つけた場合は、決して素手で触らず、自治体の指定する方法に従って慎重に駆除してください。
万が一、毒針毛に触れてしまった可能性がある場合は、こすらずにセロハンテープなどでそっと毛を取り除き、流水でよく洗い流してください。症状がひどい場合は、速やかに皮膚科を受診しましょう。
まとめ:パンジーの毛虫対策は正体確認から
- パンジーにつく黒とオレンジの毛虫の多くはツマグロヒョウモンの幼虫
- ツマグロヒョウモンはヒョウ柄の美しい蝶になる
- 幼虫のトゲトゲした見た目に反して毒はない
- 直接触るとトゲが刺さって痛いことがあるので注意が必要
- 駆除する場合は割り箸で捕獲するか園芸用の殺虫剤を使用する
- 薬剤は予防効果のある粒剤と即効性のあるスプレー剤がある
- 薬剤を使用する際は必ず説明書を読み安全対策を徹底する
- 発生を防ぐには防虫ネットが効果的
- もし毛がフサフサしていたら毒を持つドクガの可能性が高い
- ドクガの仲間は毒針毛を持っており非常に危険
- 毒毛虫には絶対に素手で触れない
- 毛虫の種類を正しく見分けることが最も重要
- ツマグロヒョウモンは温暖化などで都市部に適応し増えている
- アシナガバチやカマキリなどが天敵として知られている
- パンジーの毛虫対策はまず相手の正体を知ることから始める