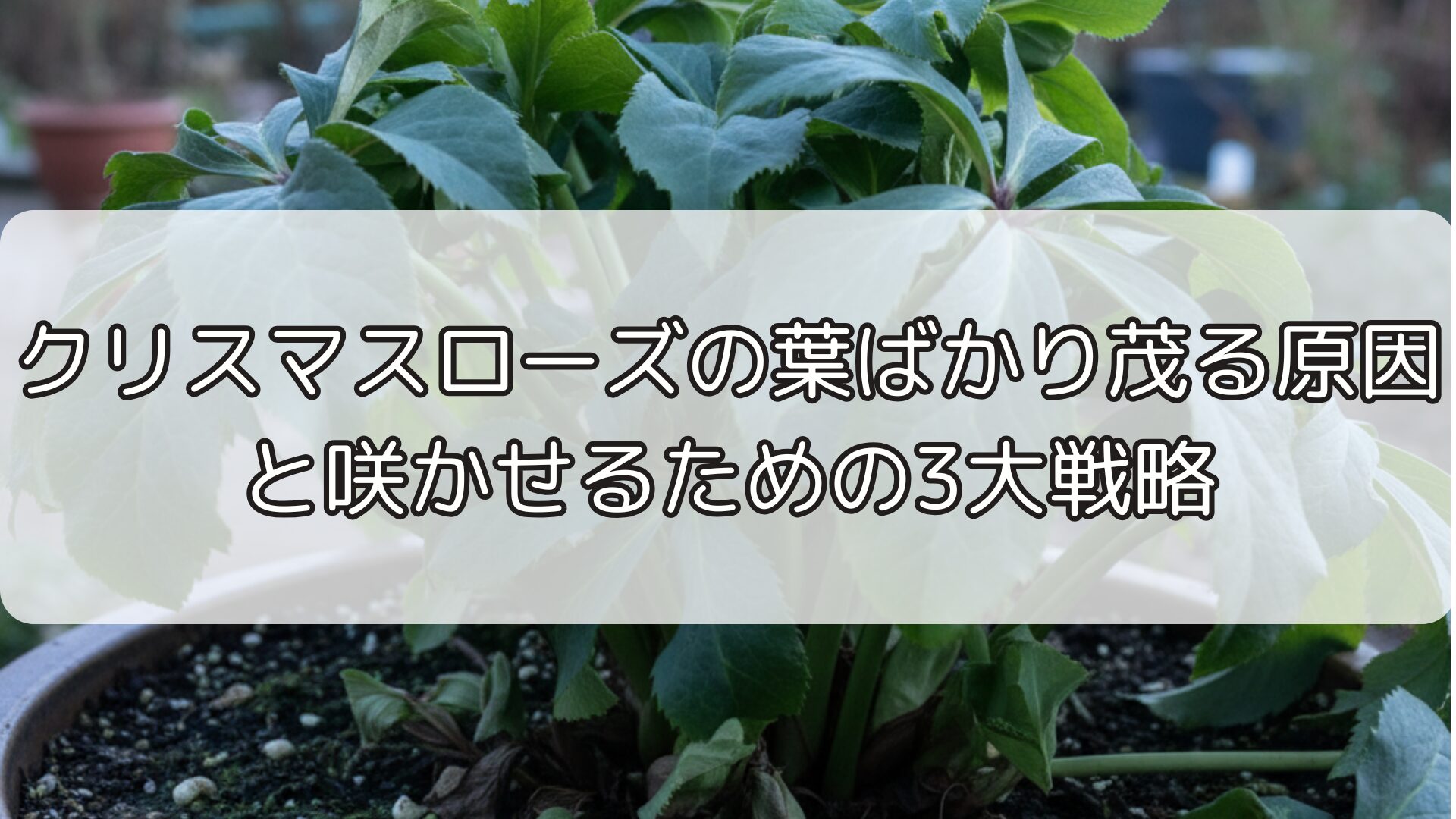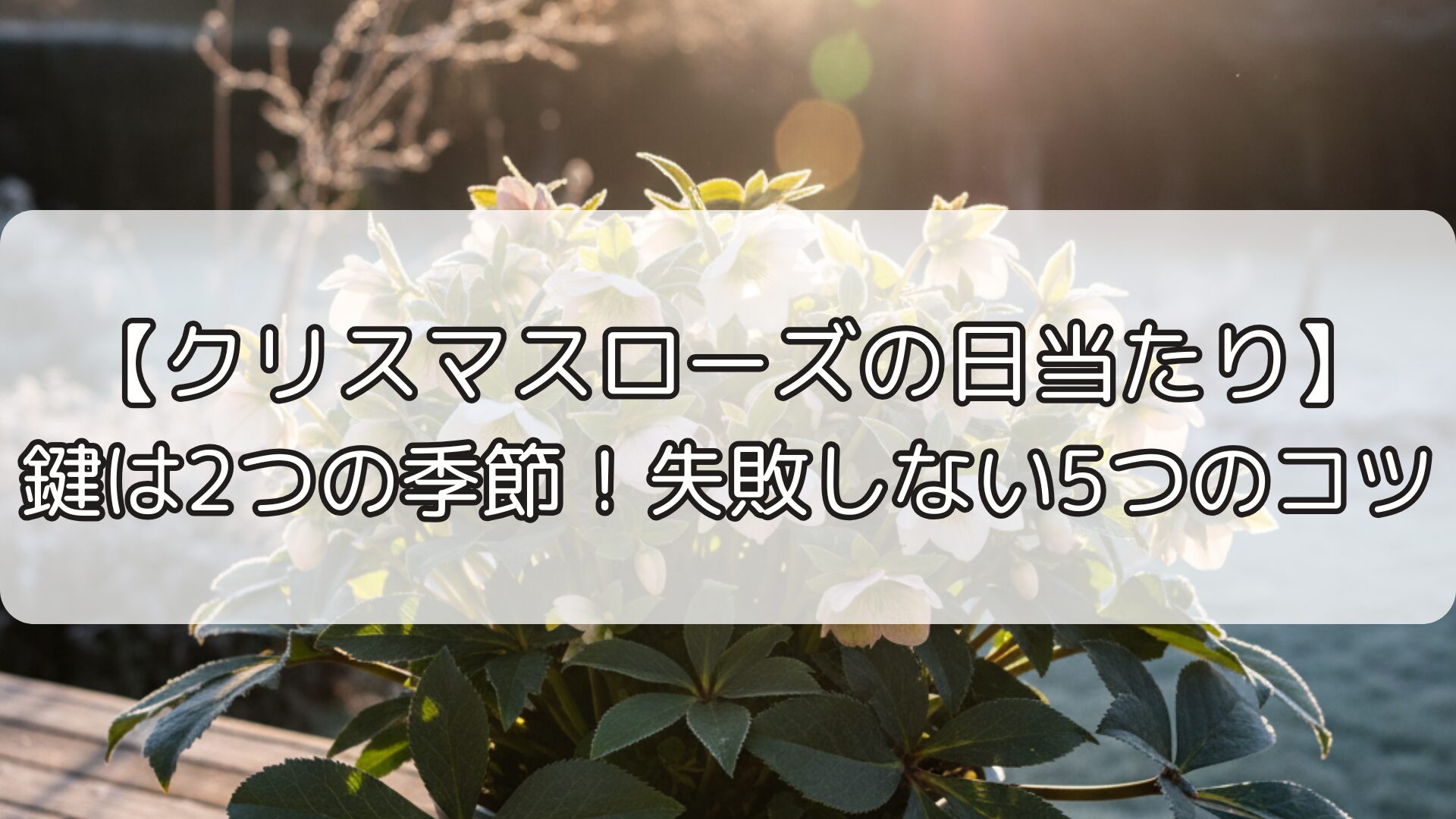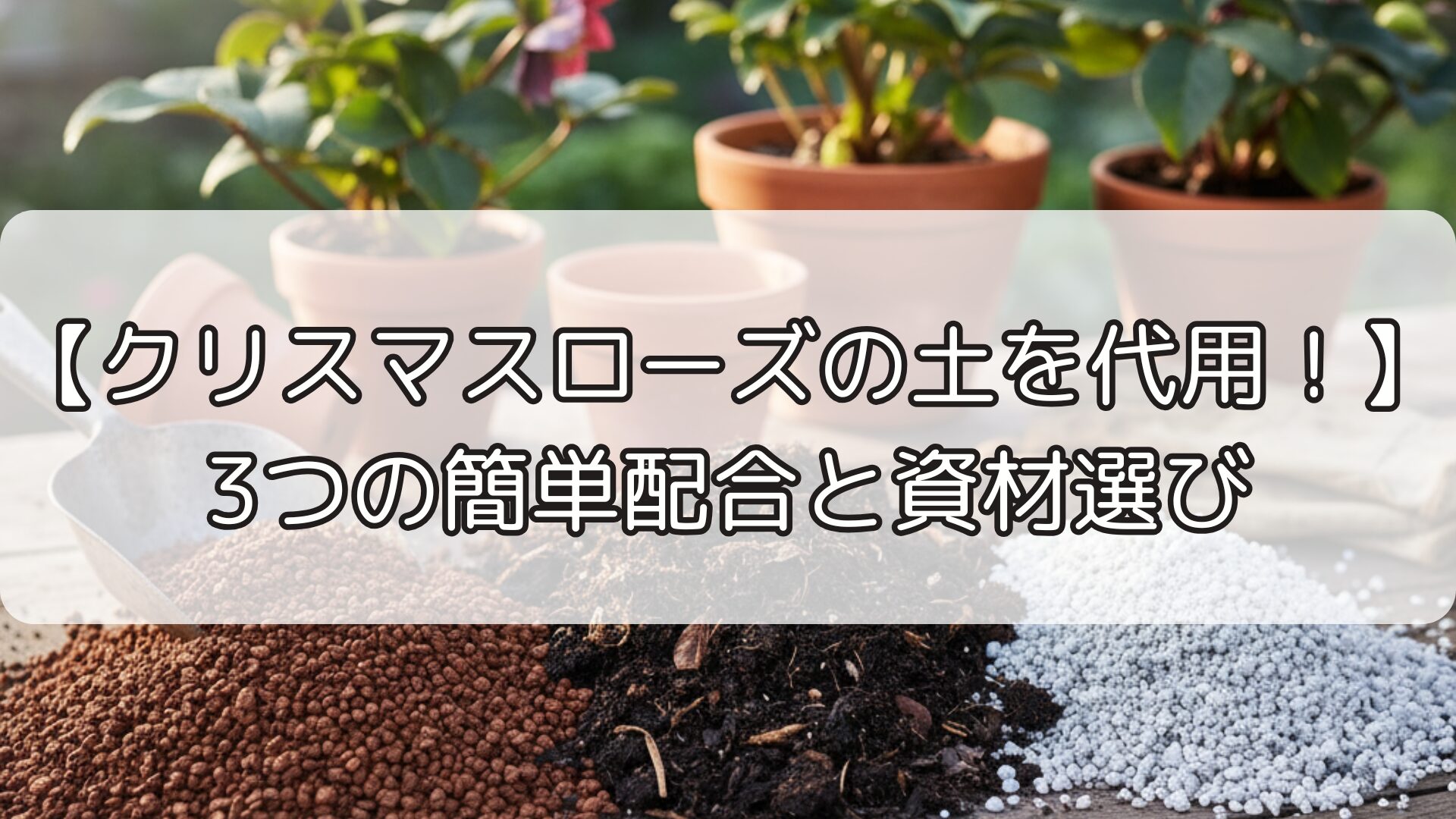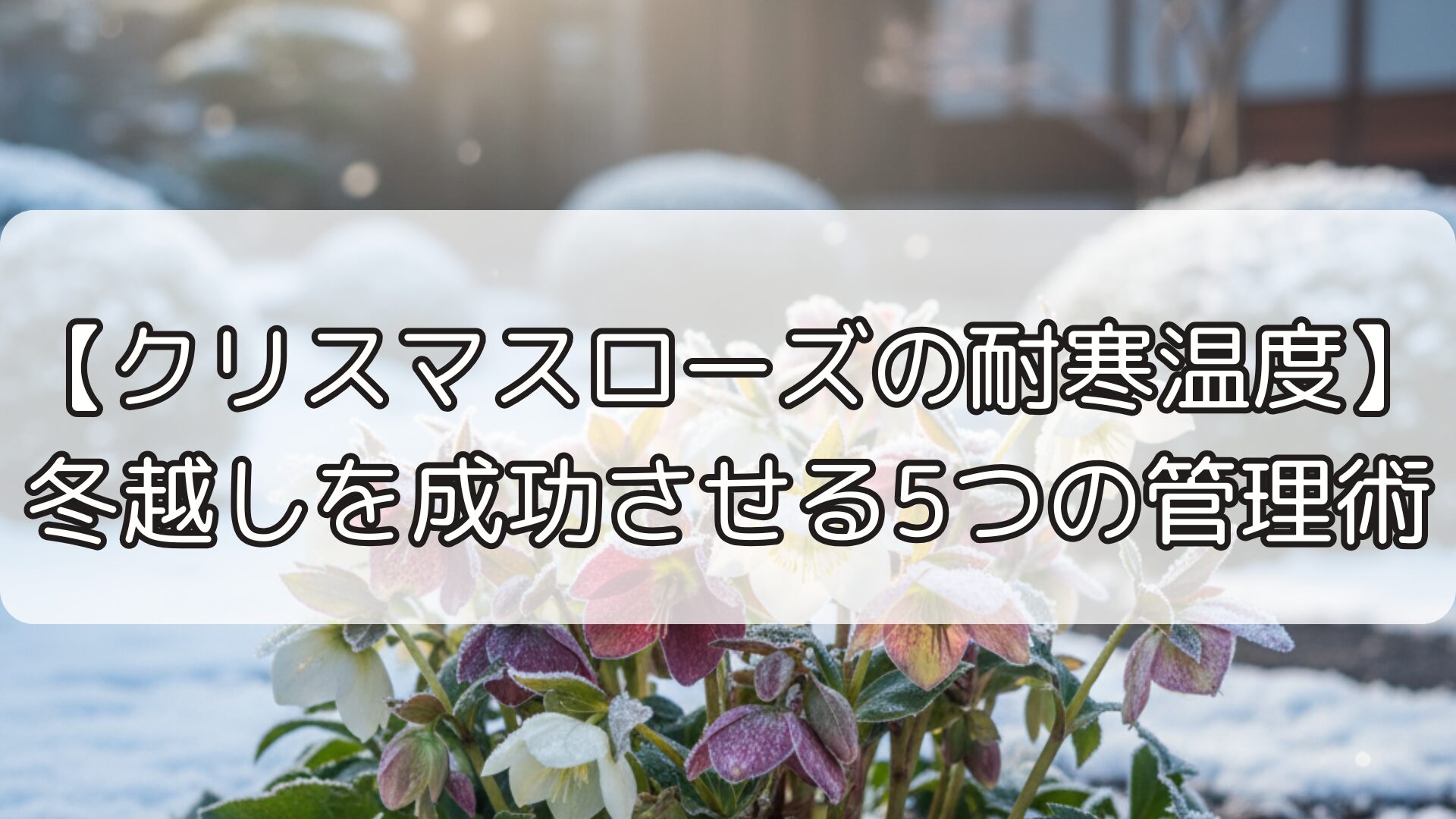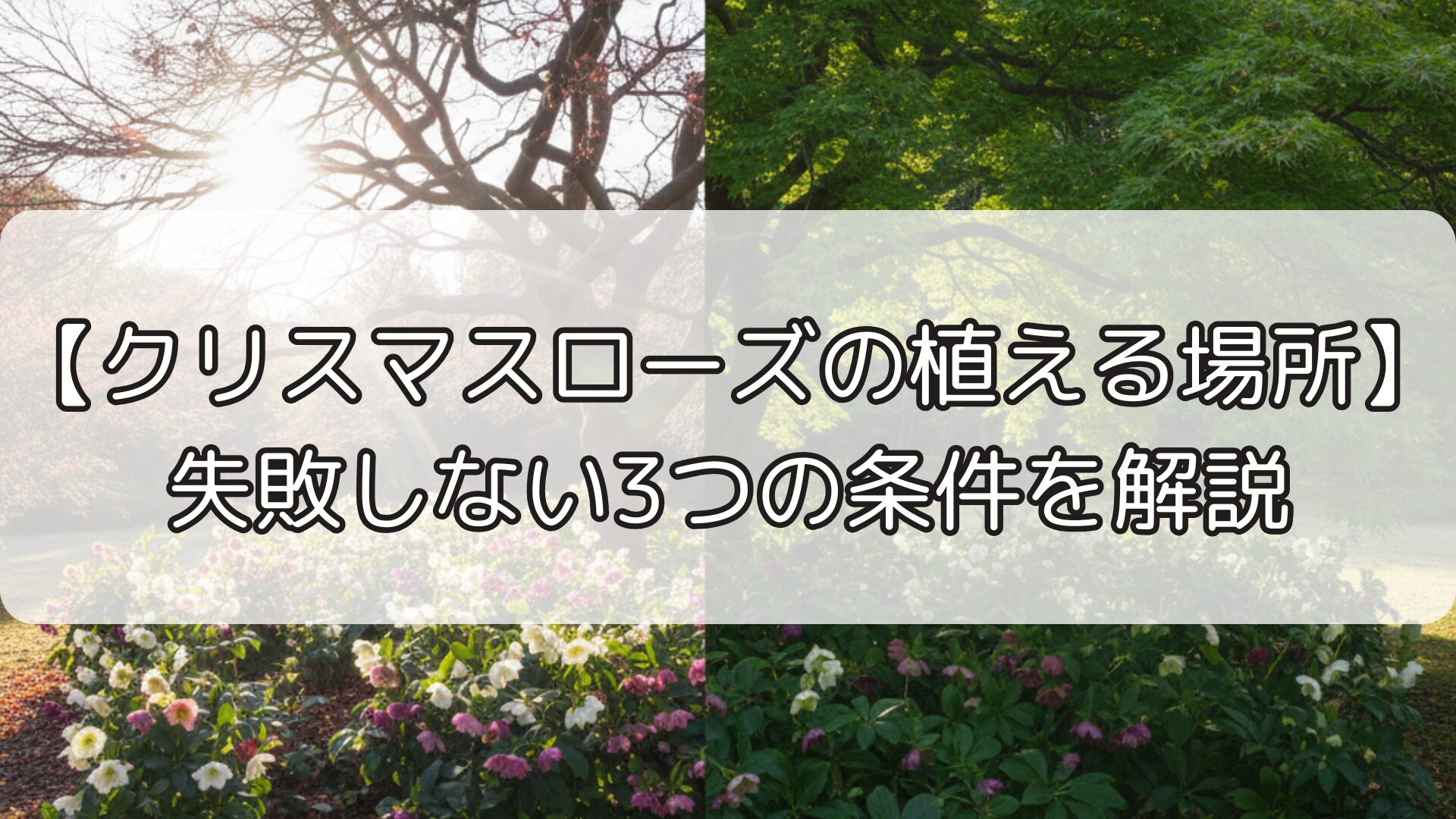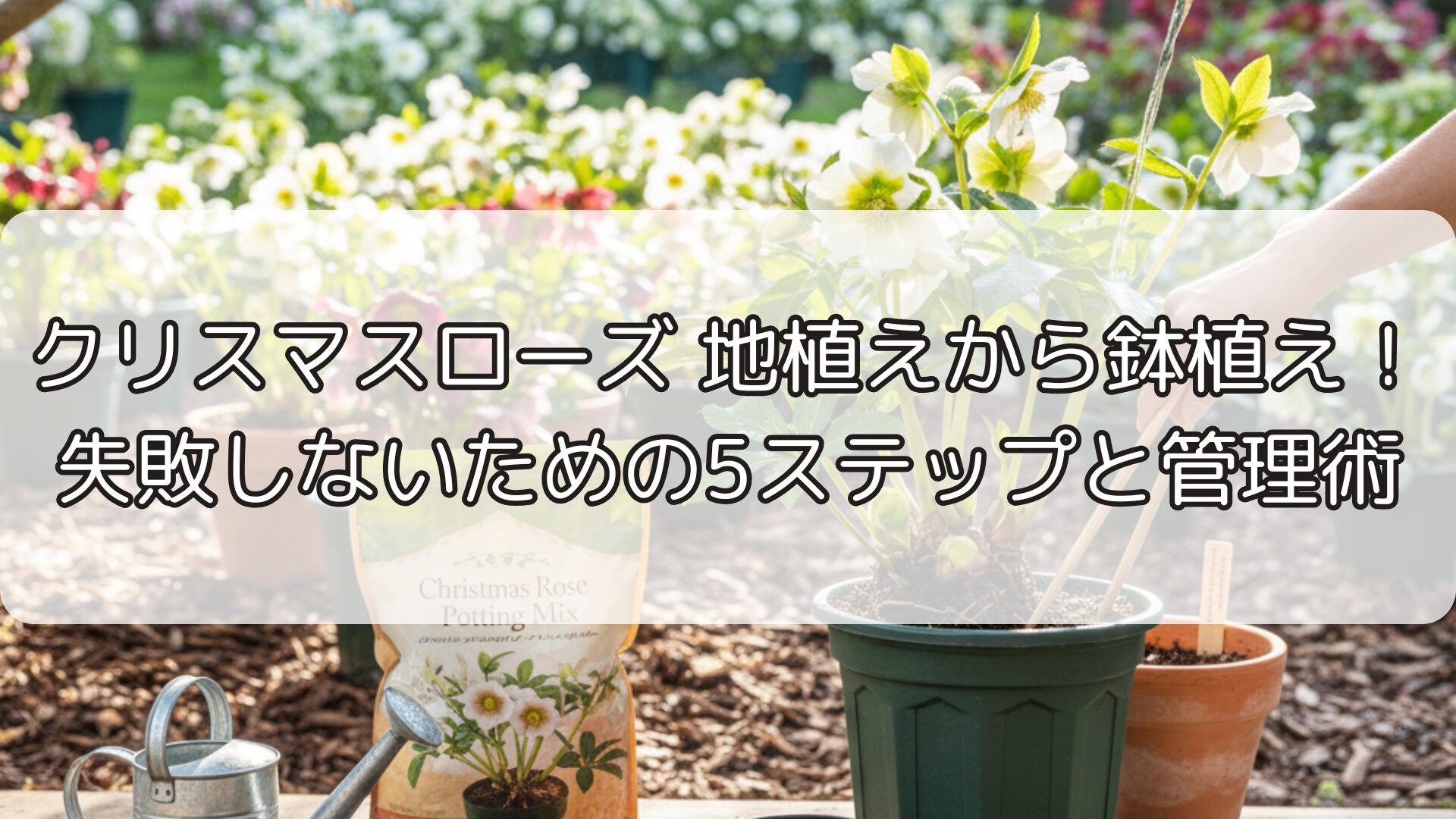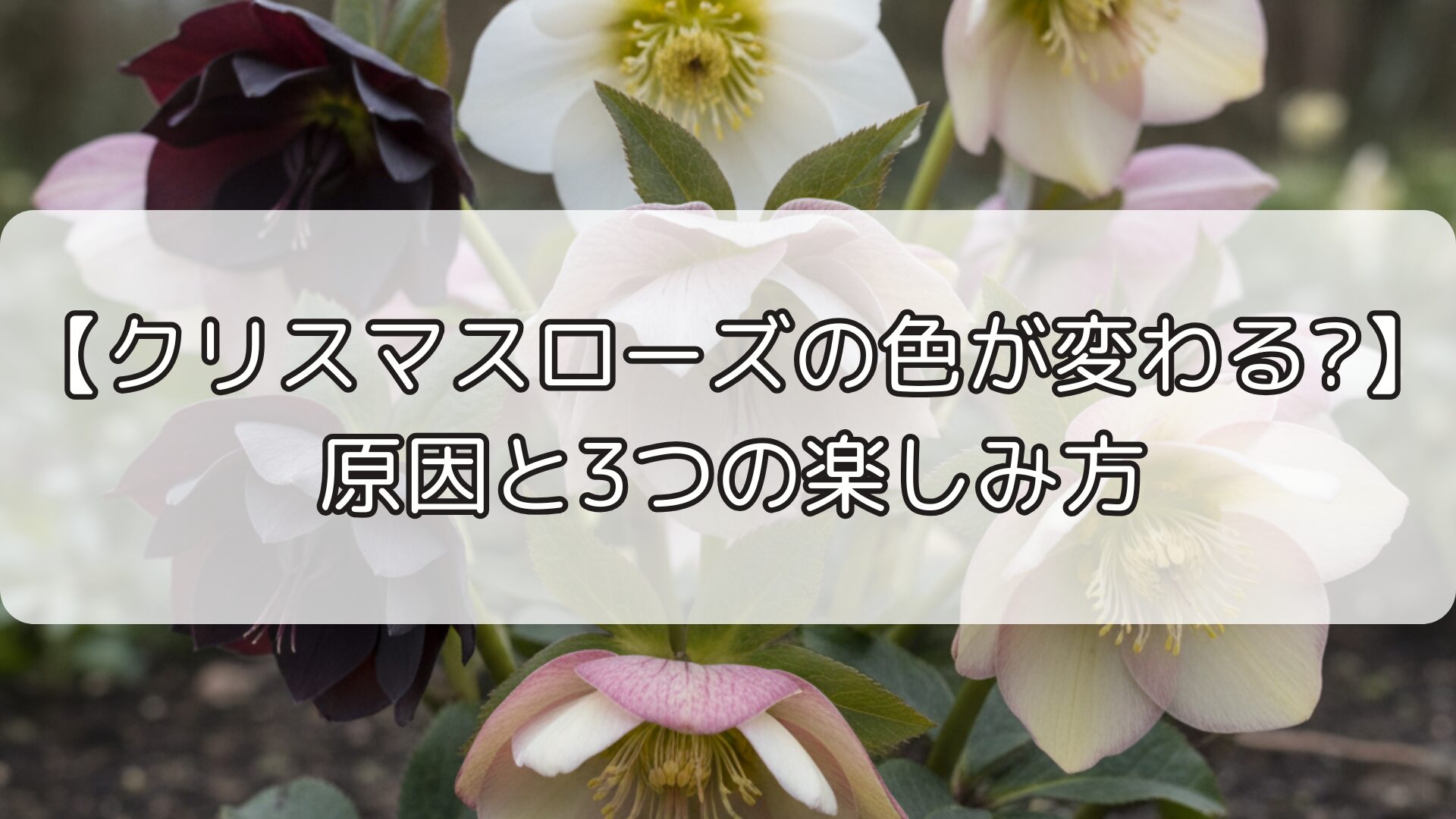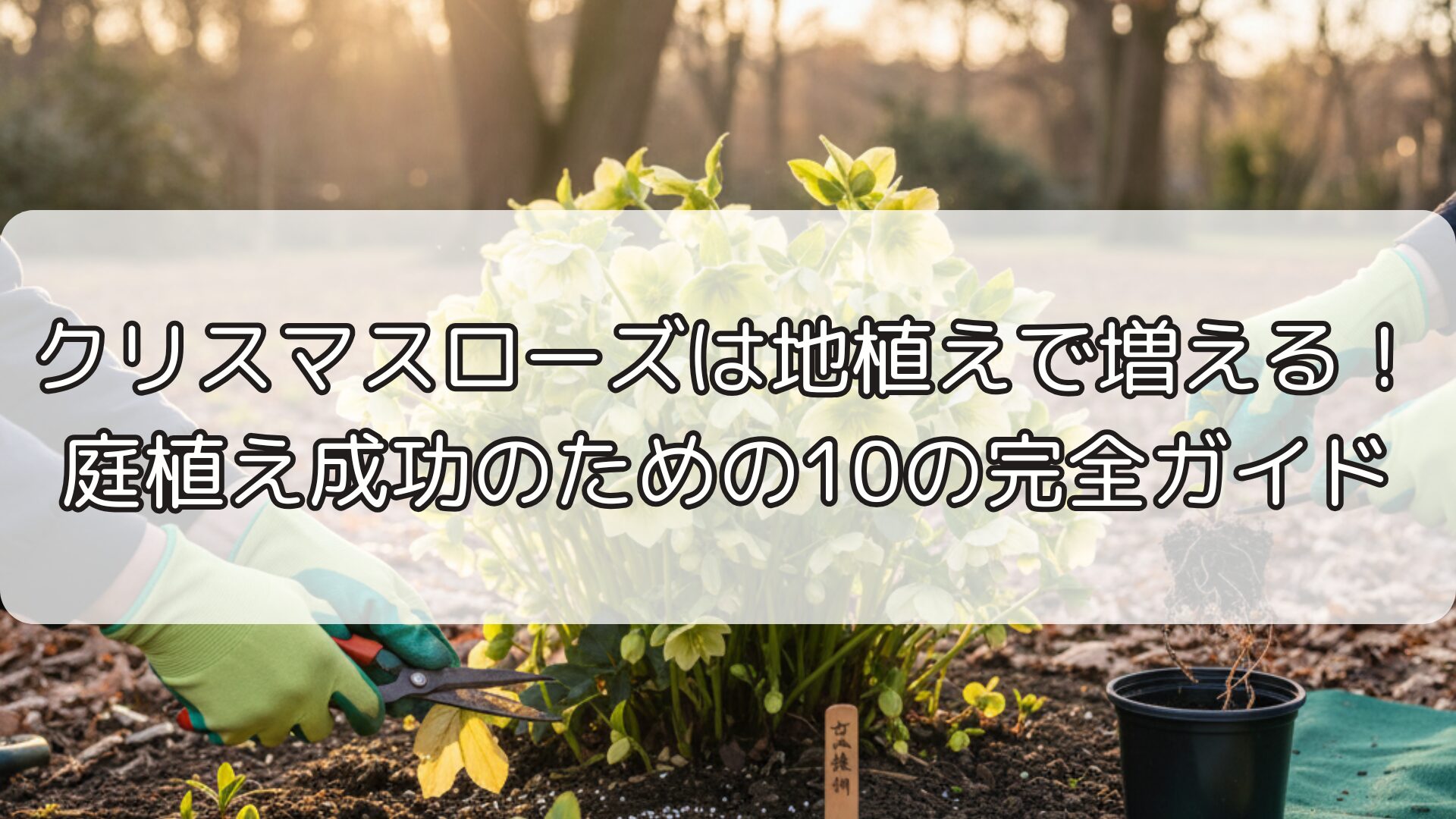クリスマスローズはなぜクリスマスに咲かない?本当の理由と5つの豆知識
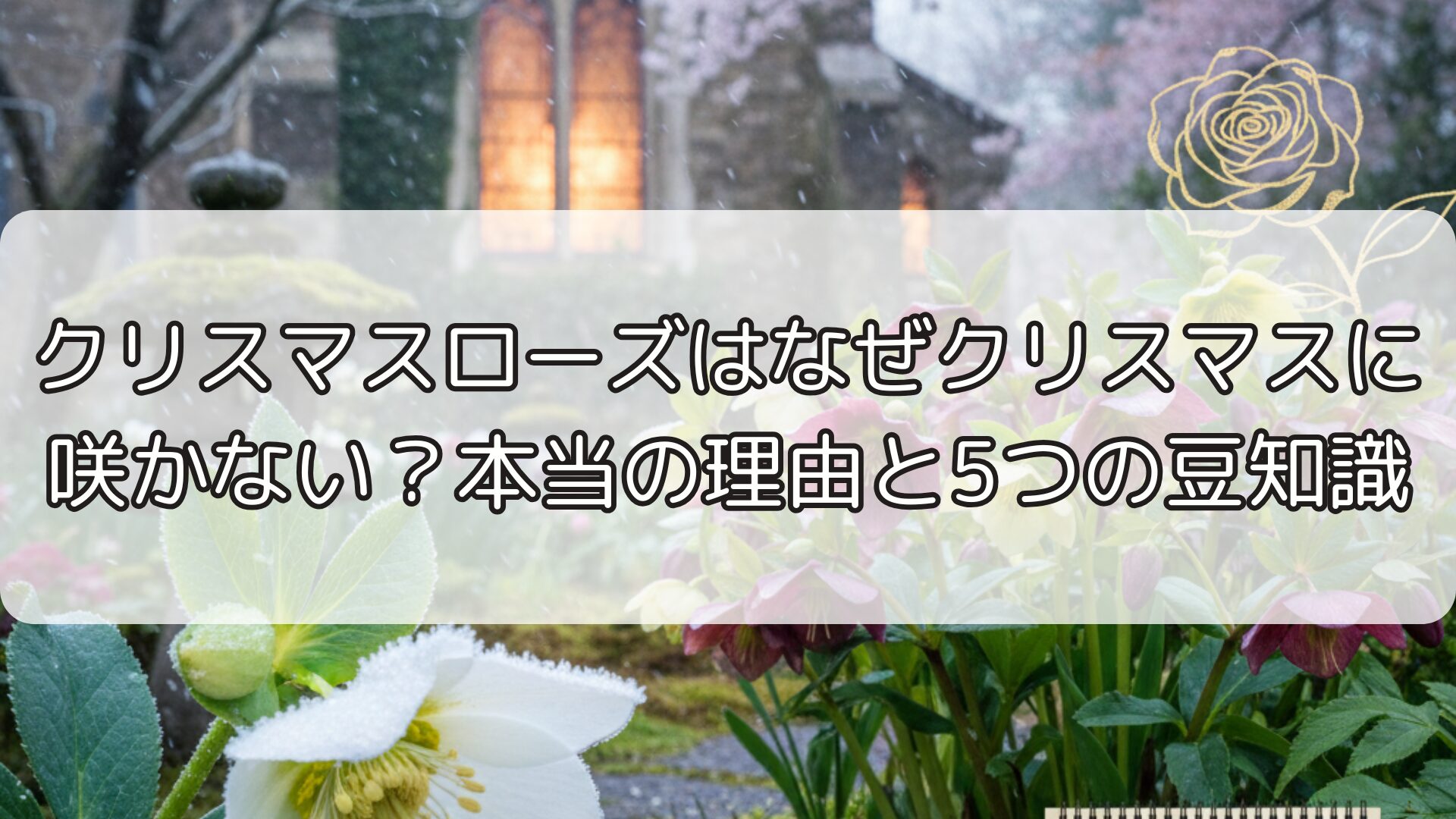
クリスマスローズという名前を聞くと、多くの方がクリスマスの時期に咲くバラを想像するかもしれません。しかし、実際には日本のクリスマスに咲かないことが多く、「なぜクリスマスローズという名前なの?」と疑問に思う方も少なくありません。
この記事では、クリスマスローはなぜクリスマスと呼ばれるようになったのか、その感動的な名前の由来から、なぜクリスマスに咲かないのかという疑問までを掘り下げます。本来クリスマスローズと呼ばれていたニゲルという品種、そして春に咲く品種の別名や和名についても解説。
さらに、花がなぜ下向きに咲くのかという素朴な疑問や、誕生花としての側面、基本的な育て方のポイントまで、クリスマスローズに関する情報を網羅的にお届けします。
- クリスマスローズという名前の本当の由来
- 日本で流通する品種がクリスマスに咲かない理由
- 花が下を向く理由や花言葉、和名などの豆知識
- 基本的な育て方のコツ
クリスマスローズはなぜクリスマス?その名前の秘密

- 実はクリスマスに咲かない?
- 感動的な名前の由来
- 本来の種類、ヘレボルス・ニゲル
- レンテンローズという別名
- 「寒芍薬」という美しい和名
実はクリスマスに咲かない?

クリスマスローズという名前なのに、クリスマスの時期に咲いているのをあまり見かけない、と感じたことはありませんか?
それもそのはず、現在日本で「クリスマスローズ」として広く流通している品種の多くは、実際の開花期が2月から4月頃です。これらは「オリエンタリス」という品種や、それを親とした交配種(ガーデンハイブリッド)が中心となります。
では、なぜ春咲きの花が「クリスマス」の名前で呼ばれるようになったのでしょうか。その理由は、この花の「本来の名前」と、日本での「流通名」の違いに隠されています。
私たちが「クリスマスローズ」と呼んでいる花の多くは、厳密には違う名前を持っていたのです。
感動的な名前の由来

クリスマスローズの名前の由来には、キリストの誕生にまつわる感動的な神話が関係しています。
イエス・キリストが誕生した夜、マデロンという貧しい羊飼いの少女が祝福に訪れようとしました。しかし、他の人々が高価な贈り物を持参する中、貧しい彼女は捧げるものを何も持っていませんでした。
贈り物ができず悲しみに暮れるマデロンが涙を流すと、その涙が落ちた地面から、純白の美しい花(ニゲル)が咲き始めました。マデロンは喜んでその花を摘み、幼子キリストと聖母マリアに捧げたということです。
この伝説から、クリスマスの時期に咲くこの花は「キリスト(クリスマス)に捧げられたバラ(ローズ)」として、「クリスマスローズ」と呼ばれるようになったとされています。
ちなみに、「ローズ」とついていますが、バラ科ではなくキンポウゲ科の植物です。これは、花の形がバラに似ていたことに由来すると言われています。
本来の種類、ヘレボルス・ニゲル

前述の通り、クリスマスローズという名前は、もともとある特定の1品種だけを指す愛称でした。
それが、キンポウゲ科ヘレボルス属の原種である「ヘレボルス・ニゲル(Helleborus niger)」です。この「ニゲル」こそが、本当のクリスマスローズなのです。
ニゲルは、ヨーロッパの原産地において、まさにクリスマスの時期(12月頃)から咲き始める早咲きの性質を持っています。花の色は純白で、伝説の通り清楚な姿をしています。
「ニゲル」という種小名はラテン語で「黒い」という意味ですが、これは花の色ではなく、根が黒いことに由来しています。
レンテンローズという別名

一方、私たちが日本でよく目にする、春(2月〜4月)に咲くカラフルな品種群(オリエンタリス系ハイブリッド)には、別の愛称があります。
それが「レンテンローズ(Lenten Rose)」です。
「レント(Lent)」とは、キリスト教においてイースター(復活祭)までの約40日間を指す「四旬節(しじゅんせつ)」のこと。このレンテンローズは、まさにその四旬節の時期に咲くバラ、という意味で名付けられました。
つまり、ヨーロッパではクリスマスの時期に咲く「ニゲル(クリスマスローズ)」と、春先に咲く「オリエンタリス系(レンテンローズ)」は、明確に区別されて呼ばれていたわけです。
しかし、日本ではヘレボルス属の植物全体を総称して「クリスマスローズ」と呼ぶ習慣が定着しました。そのため、「クリスマスに咲かないクリスマスローズ」という、時期のズレが生じてしまったのです。
「寒芍薬」という美しい和名

クリスマスローズが日本に渡来したのは、意外にも古く、明治初期から江戸末期頃とされています。当時は観賞用としてではなく、薬用植物として移入されたようです。
その後、茶人たちの間でそのうつむいて咲く風情が好まれ、茶花として一部で楽しまれるようになりました。
その際、原種のニゲルには「初雪おこし(はつゆきおこし)」という和名が、そして春咲きの交配種(オリエンタリス系)には「寒芍薬(かんしゃくやく)」という美しい和名が付けられました。
「寒芍薬」とは、寒い時期に芍薬(しゃくやく)のような花を咲かせる、という意味が込められています。今でもこの和名で呼ばれることがあり、その風情ある響きに魅了されるファンも少なくありません。
クリスマスローズ |なぜクリスマスの謎

- 日本で流通する主な品種
- 花がなぜ下向きに咲くのか
- 誕生花と素敵な花言葉
- 育て方の基本ポイント
日本で流通する主な品種

現在、日本の園芸店などで「クリスマスローズ」として販売されているものの多くは、「ガーデンハイブリッド(オリエンタリス・ハイブリッド)」と呼ばれる交配品種群です。
これらは主に春咲きの「ヘレボルス・オリエンタリス」を親として、様々な原種が交配されて生まれました。特徴は、花色や花形が非常に豊富なことです。白、ピンク、赤、紫、緑、黄色、黒に近い色まであり、咲き方も一重、八重(ダブル)、半八重(セミダブル)など多岐にわたります。
本来のクリスマスローズである「ニゲル」も流通していますが、ガーデンハイブリッドに比べると数は少なめです。
主な品種の違い(まとめ)
混乱しやすい2つの主な系統について、特徴を表にまとめます。
| 項目 | ニゲル(本来のクリスマスローズ) | ガーデンハイブリッド(レンテンローズ) |
|---|---|---|
| 主な開花期 | 12月~2月頃(早咲き) | 2月~4月頃(春咲き) |
| 主な花色 | 白(咲き進むとピンクを帯びる) | 白、ピンク、赤、紫、緑、黄、黒など多彩 |
| 咲き方 | 横向き~やや下向き | 多くは下向き(品種改良で横向きも) |
| 葉の特徴 | 常緑性。やや肉厚。 | 常緑性だが、古葉は冬に枯れることも。 |
花がなぜ下向きに咲くのか

クリスマスローズの大きな特徴の一つが、うつむくように下向きに咲くことです。奥ゆかしく可憐な姿ですが、「なぜ下を向いているの?」と疑問に思うかもしれません。
これには、植物が生き残るための合理的な理由があると考えられています。
- 花粉を守るため
クリスマスローズが咲くのは、まだ寒さが残る冬の終わりから早春です。この時期は雨や雪が降ることも多いため、花が上を向いていると、中心部にある大事な花粉や雌しべが濡れてしまい、受粉がうまくいかなくなります。下を向くことで、雨や雪から花粉を守っているのです。 - 受粉を助ける昆虫のため
この時期に活動する主な受粉者(ポリネーター)は、ミツバチやマルハナバチなどです。これらのハチは、下向きに咲く花を好み、花の中に潜り込むようにして蜜を集める習性があると言われています。ハチにとって効率よく蜜を集められる形に進化することで、受粉の確率を高めていると考えられます。
最近では品種改良が進み、横向きや、やや上向きで咲く品種も登場しています。
誕生花と素敵な花言葉

クリスマスローズは、その背景にある伝説や開花時期から、いくつかの日付の誕生花とされています。
代表的な日付としては、11月16日、12月13日、12月19日、12月26日など、複数の説があります。特にクリスマスの時期に近い日付が多く挙げられます。
花言葉も、そのうつむき加減の姿や伝説に由来するものが多く、非常に情緒的です。
- 「私の不安をとりのぞいてください」
- 「慰め」
- 「追憶」
- 「私を忘れないで」
これらの花言葉は、かつてヨーロッパで戦地へ向かう兵士が、残していく恋人にこの花を贈った習慣に由来するとも言われています。
一方で、クリスマスローズには「中傷」という少し怖い花言葉もあります。これは、次に解説する「有毒性」が関係しているとされています。
育て方の基本ポイント

クリスマスローズは、いくつかの重要なポイントさえ押さえれば、初心者でも比較的育てやすい丈夫な宿根草です。毎年美しい花を咲かせるための、基本的な育て方をご紹介します。
1. 置き場所(日当たり)
クリスマスローズの育て方で最も重要なのが、季節に合わせた日当たり管理です。
- 秋〜春(10月〜4月):生育期にあたるため、日当たりが良い場所で管理します。日光を十分に浴びることで、花芽がしっかりと育ちます。
- 夏(5月〜9月):高温多湿と強い直射日光が苦手です。この時期は明るい半日陰(日陰)に移動させます。地植えの場合は、落葉樹の木陰など、夏は葉が茂って日陰になり、冬は葉が落ちて日なたになる場所が最適です。
2. 水やり
水やりは、鉢植えと地植えで異なります。
- 鉢植えの場合:生育期(10月〜5月)は、土の表面が乾いたら鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えます。休眠期(6月〜9月)は、根腐れを防ぐため、やや乾かし気味に管理します。
- 地植えの場合:一度根付いてしまえば、基本的には雨水だけで十分です。ただし、夏場に乾燥が続く場合は、朝晩の涼しい時間帯に水を与えてくださ
3. 肥料
クリスマスローズは肥料を好む植物です。適切な時期に肥料を与えることで、花付きが格段に良くなります。
- 固形肥料(緩効性):年に3回、10月頃(植え替え時)、12月頃、2月頃(花の後)に株元に置きます。
- 液体肥料:生育期(10月〜4月)に、月に2〜3回程度、水やり代わりに与えるとより効果的です。
夏(6月〜9月)は肥料を与えないでください。弱っている根を傷める原因になります。
4. 古葉取り(こばとり)
美しい花を咲かせ、病気を防ぐために欠かせない作業が「古葉取り」です。
- 時期:11月〜12月頃、株元から新しい芽(新葉)が動き出したら行います。
- 方法:前年に伸びた古い葉(硬く、色が濃い葉)を、地際(根元)から切り取ります。
- 目的:新芽に日光が当たるようにするため、風通しを良くして病気(特に灰色かび病)を防ぐためです。
この古葉取りを行うと、株の中心に光が当たり、春に咲く花の姿も非常に美しくなりますよ。
【最重要】有毒性に関する注意点
クリスマスローズは、その美しい姿とは裏腹に、全草(特に根)に有毒な成分を含むことが知られています。
東邦大学薬学部付属薬用植物園などの情報によると、ヘレブリンやヘレボリンといった強心配糖体が含まれており、誤って摂取すると、嘔吐、下痢、腹痛、めまい、重篤な場合には心臓麻痺などを引き起こすとされています。
(参照:東邦大学 薬学部付属薬用植物園、公益社団法人東京生薬協会)
また、植物の汁が皮膚に付くと炎症やかぶれを起こすことがあります。古葉取りや植え替えなどの作業をする際は、必ず手袋を着用してください。
小さなお子様や、犬・猫などのペットがいるご家庭では、誤って口にしないよう、置き場所や管理に最大限の注意が必要です。
まとめ:クリスマスローズ なぜクリスマスかの答え
- クリスマスローズという名前はキリスト誕生の伝説に由来する
- 本来クリスマスローズとは冬咲きの「ニゲル」という原種を指す
- ニゲルはクリスマスの頃に白い花を咲かせる
- 日本で広く流通しているのは春咲きの「オリエンタリス系」
- オリエンタリス系は「レンテンローズ」という別名を持つ
- レント(四旬節)の時期に咲くためレンテンローズと呼ばれる
- 日本ではヘレボルス属全体を「クリスマスローズ」と呼ぶため季節のズレが生じた
- 「ローズ」と付くがバラ科ではなくキンポウゲ科の植物
- 和名には「寒芍薬(かんしゃくやく)」や「初雪おこし」がある
- 花が下を向くのは雨や雪から花粉を守るためとされる
- 誕生花は12月13日や12月26日など諸説ある
- 花言葉は「私の不安をとりのぞいてください」「慰め」など
- 「中傷」という花言葉は有毒性に由来すると言われる
- 育て方の鍵は夏越し(夏は半日陰、冬は日なた)
- 11月〜12月の「古葉取り」が花付きと病気予防に重要
- 全草に毒性があるため手袋を着用し誤食に厳重注意する